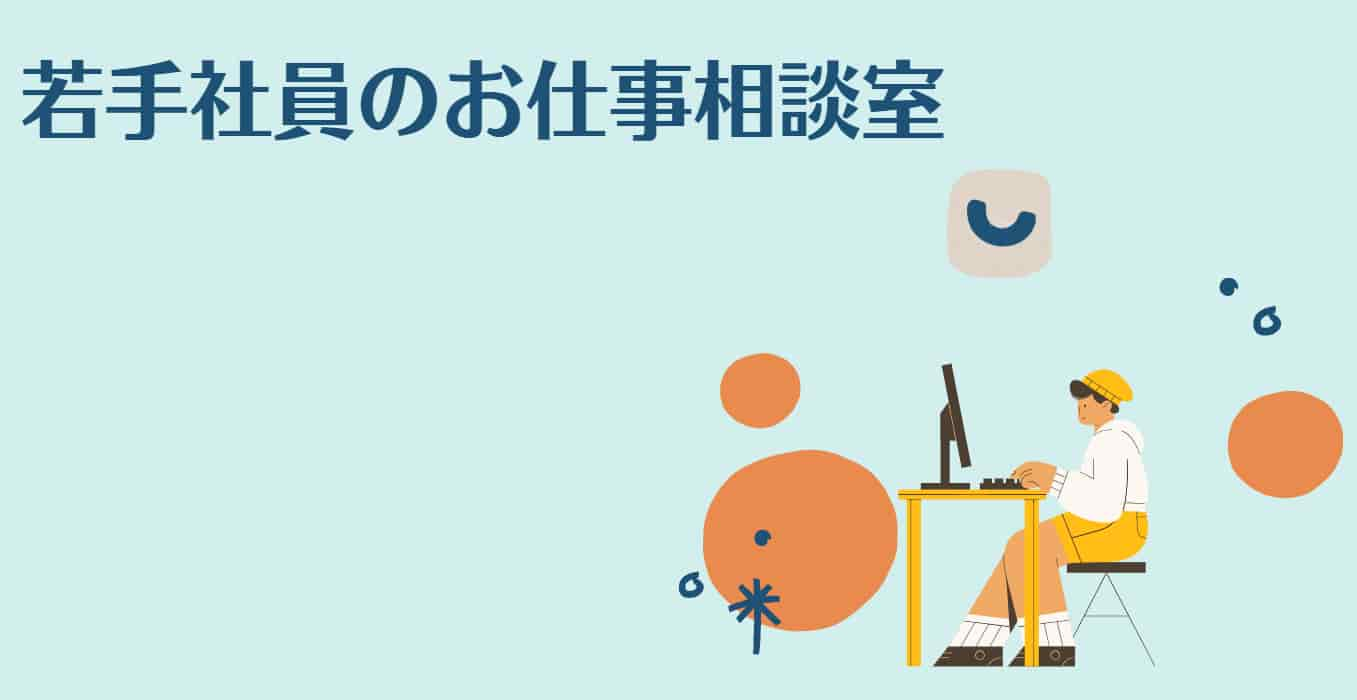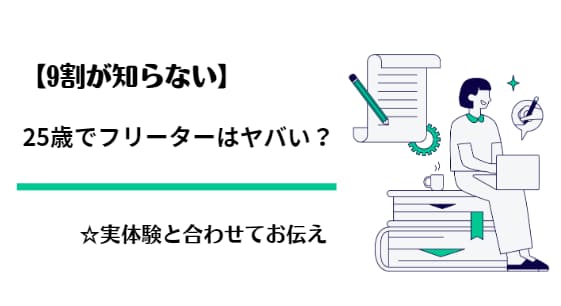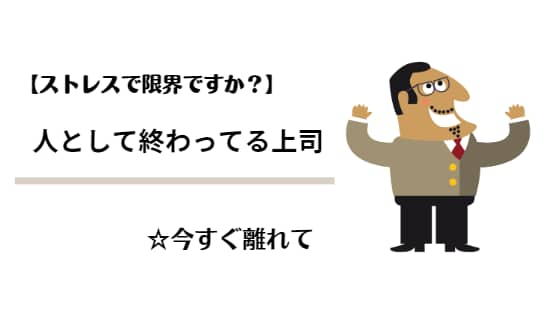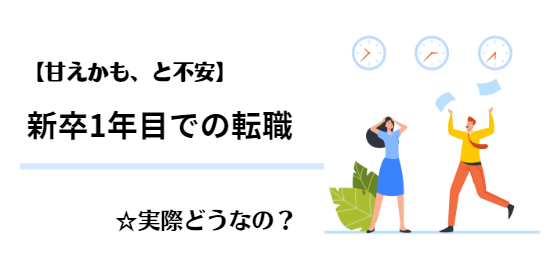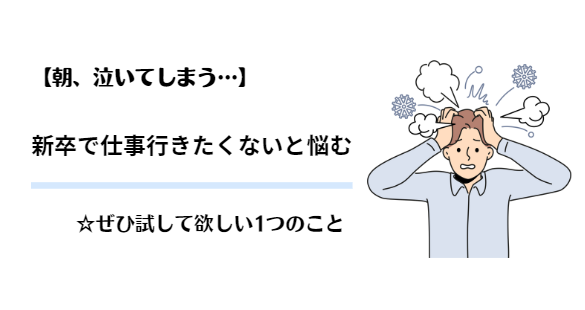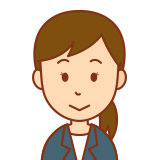
最近、あんまり仕事がない…。
将来とか少し不安。
と、会社にいるのに仕事がない、いわゆる「社内ニート」になってお悩みでしょうか?
社会人たるもの忙しくはなくとも、普通に仕事して、ボチボチ評価されたいですよね。
ですが、「社内ニート」になってしまったら、少し危機感を持った方がいいです。
というのは、忙しくなったときに、仕事は任されるかもしれないけど、腕が鈍ってる可能性があるから。
私なんて、新卒で配属されてから、ほぼずっと社内ニートでしたが、日の目をみることはありませんでしたし…。
本記事では、「新卒で社内ニートだった私の末路」と「社内ニートの対策」までお伝えするので、ぜひ最後までご覧ください。
新卒で社内ニートになった私の末路

私は新卒で「社内ニート」
いわゆる、「仕事がない」状態で、ほぼ毎日定時帰りでした。
そんな私の末路は…
1年半で退職
1年半で退職、です。
ずっとヒマしてても埒(らち)が明かないと、考えました。
周りには、
「新人なんてそんなもん」
「忙しいときは必ずくるよ」
なんて言われてましたが、チームとしては休日出勤もしてるくせに、私には一向に声がかからずだったので決断しました。
(あっ、俺って必要ないやん…と。)
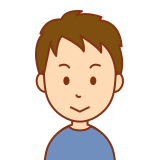
上司からは「これからだよ」と言われましたが、やめました。
辞めた後は、フリーランスに転身。
しかし、
そうカンタンにいくワケもなく、フリーランスからフリーターという道をたどりました。
関連記事:【9割が知らない】25歳でフリーターはヤバいと言われる意外な真相
社内ニートなって気づいた会社員の3つのリアル
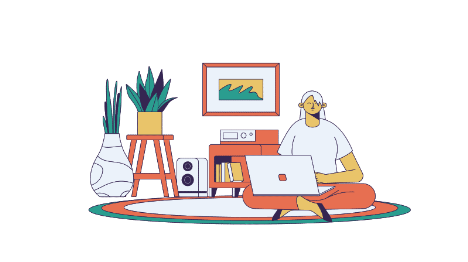
新卒で社内ニートになって、1年半で退職した私の末路は、フリーターでした。
厳密には、バイトしながら、ライター / ブロガーもやってます。
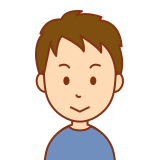
個人的に「後悔」は1ミリもないです。
が、傍から見たら、真似したくない生き方で、負け組かもしれませんね(笑)
でも、
社内ニートって、本当ロクなことがなく、耐えられませんでした…。
本項では、そんな私が社内ニートになってわかった「リアル」をお伝えします。
- 仕事は「できる人」に振られていく
- 誰も構ってくれない
- 仕事の腕は上がらない
順番にみていきましょう。
①仕事はできる人に振られる
仕事って、優秀な人に振られるんですよね。
仕事を振る側からの「信頼」があるから、です。
だから、「いつか仕事くるっしょ」とか思ってたら、きませんでした。
新卒で社内ニートになった私は、上司からみて「信頼できる存在」ではないので、当然なのでしょうが。
(※もちろん、文句は言いたいです。多少のミスは目瞑ってでも、任せてくれないもんかね、と。)
②誰も構ってくれない
でも、誰も構ってくれないんですよね。
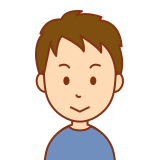
構う余裕がない、というか。
2年目で仕事振られないなら環境を変えた方がいい3つのワケでもお伝えしていますが、空気みたいな扱いなワケです。
だから、仕事したいなら「くれ!」って言って、最悪奪うくらいの感覚でいないとダメでした。
(まあ、そこまでしてやりたい仕事でもないわ、ということなら、その程度の仕事というコトなので、転職しましょう。)
あと、そもそも、
「アイツ暇そうにしてんな」
「いっちょ、仕事任せてみるか」
という視野の広い上司がいる会社では、社内ニートなんて生まれません。
普通の上司なら、マネジメントがきちんとしてますから。
なので、誰かが社内ニートになる、というコトは、会社のマネジメント力にも疑問符がつくので、危機感を持った方がいいんです。
関連記事:【ストレスで限界】人として終わってる上司からは離れた方がいいワケ
③仕事の腕は上がらない
あと、社内ニートになると、仕事の腕は上がりません。
やっぱり、仕事力は「実践」に身につくものでした。
私自身、本読んだり、Excelを勉強したりはしてましたが、役立たんかった印象です。
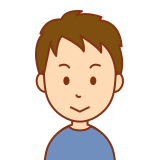
まあ、身も入らなかったですが(笑)
このように、社内ニートになると、仕事の腕は上がらないし、久しぶりの仕事がきても「失敗」が怖くなってるので、危機感を持った方がいいです。
関連記事:【社内ニートは勝ち組じゃない?】転職しないと危ない3つのワケ
社内ニートは転職すべきなのか?

ここまでの内容は、ご覧のアナタを焦らせるような内容だったかもしれませんが、あくまで私が感じてるコトです。
ただ、最悪の場合、社内ニートになると、
誰も構まわない → 仕事の腕は上がらない
結果:給料のために会社にしがみつくサラリーマンになる
こんな可能性がある、というコトは頭に入れておきましょう。
個人的には「すべき」だと思う
では、社内ニートは転職すべきかというと、個人的にはその方がいいと思います。
私は、お金のためだけに「人生の貴重な時間」を会社に費やす、というのはもったいないと思うからです。
また、実際にやめてみて、会社員以外の道を知れたことが今後の人生に生きそう、という感覚があるのも転職をすすめる理由の1つ。
環境を変えて、今の会社以外で働くことで、学べることは多いでしょう。
とはいえ、もちろん転職すれば確実に良い環境に巡り合えるワケではないので、進め方・準備も重要。
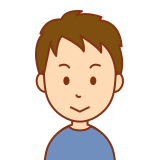
転職サイトも自分に合ったモノを選ぶ必要があります。
参考までに、転職に必要なサポートというアンケート調査(*)を、以下にまとめました。
- キャリアカウンセリング:87%
- 転職エージェント:77%
- 面接や履歴書作成の準備:37%
- ハローワーク(求人紹介):32%
- その他:10%
(* ミチサガシ「転職すべきか残るべきかの判断方法は?30代で迷ったときの判断方法を紹介」)
エージェントは使わない方がいい、という意見もありますが、転職経験者の7割以上は必要だった、と回答しています。
30代の転職経験者、と少し限定的なデータではありますが、やっぱり転職活動は1人だと心細いのでしょう。
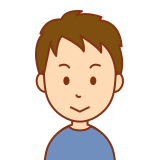
ただ、良し悪しはあるので、頼りすぎないコトも重要です。
ということで、おすすめの転職サービスは下記にまとめてみました。
参考になれば嬉しいです。
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
 |  |  | |
| サービス名 | マイナビジョブ20’s | Re就活 | doda |
| 求人数 | 4,800件~ | 10,000件~ | 200,000件~ |
| 第二新卒 | ◎ | 〇 (20代向け) | △ (全世代対象) |
| 特徴 | ・第二新卒専用転職エージェント ・未経験に強い | ・20代の転職サイト ・無料の適職診断 | ・日本最大級の転職サイト ・アドバイザーの質が高い |
さいごに

では、さいごにまとめです。
- 新卒で社内ニートだった私の末路
- 1年半で退職 → フリーランス
- でも、うまくいかずフリーター…。
- 社内ニートになってわかった「リアル」
- 仕事は「できる人」に振られていく
- 誰も構ってくれない
- 仕事の腕は上がらない
正直言って、社内ニートは勝ち組ではないです。
このままでは、あなたの大切な時間が「会社」のモノになり、その対価としてお金をもらうだけの人生になります。
これでは、
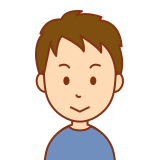
たぶん、年取ったときに後悔します、
「もっと、挑戦すればよかった」
と。
もちろん、転職すれば全て解決ではないですが、モヤモヤしているなら、ぜひ今のうちに1歩踏み出すことをおすすめさせてください。
ということで、今回は以上。
紹介した転職サービスはこちらです。
この度は、ありがとうございました!