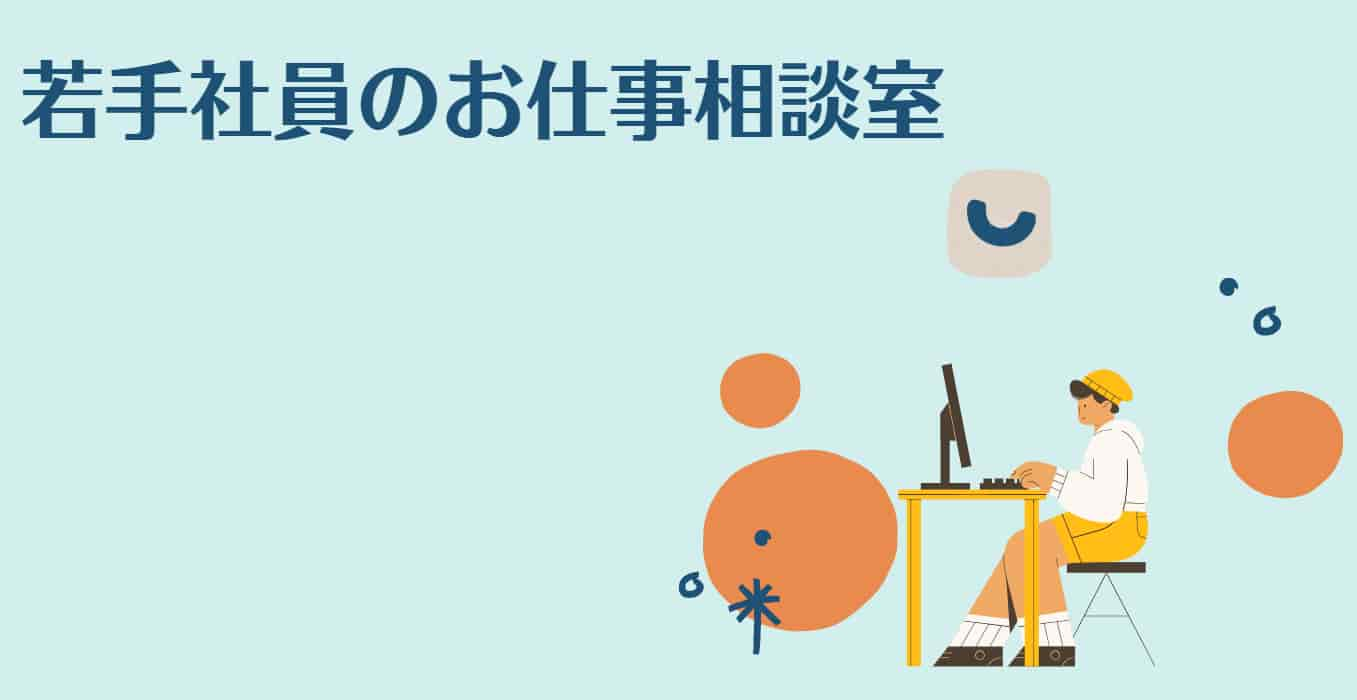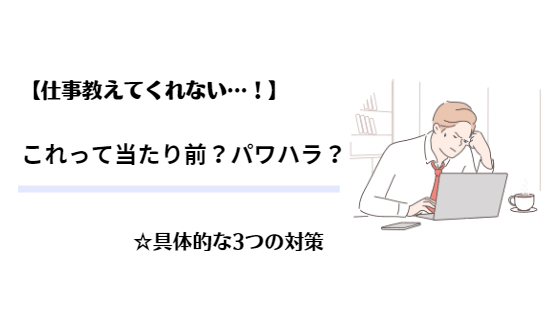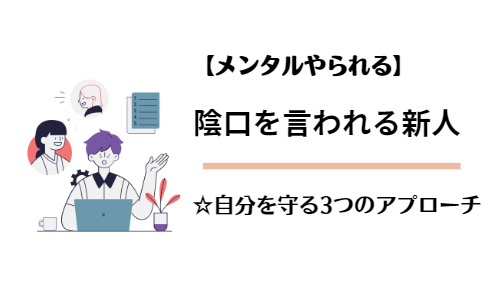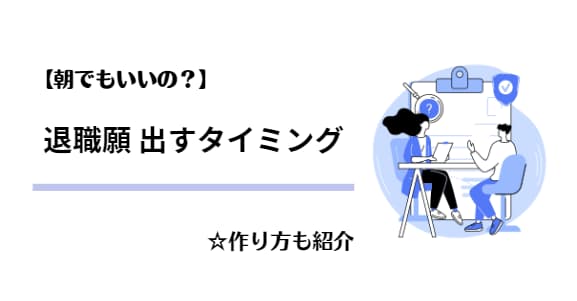「なんでも聞いて、と言っといて塩対応で草」
「マジで仕事教えてもらえん…」
本記事は、こんなお悩みを解決します。
仕事を教えてもらえず、自分のできることが蓄積されないと、キャリアへの不安が強くなりますよね。
まず、結論としては
仕事を教えてもらえないのは当たり前、ではないです。
昔の寿司屋みたいに、10年は握れないみたいなのはあり得ません。
本文では、仕事教えてもらえないときの「3つの対策」含め、詳しくお伝えしているので、ぜひ最後までご覧ください。
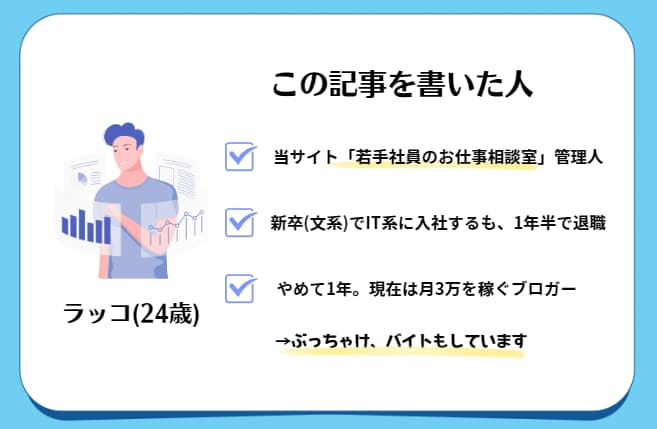
仕事教えてくれないのは当たり前ではない
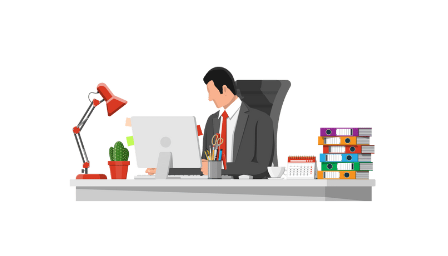
仕事を教えてもらえないのは当たり前ではないです。
「見て覚えろ」
という上司もいるけど、そんなんじゃ「転職戦国時代」の現代では、ついていく人は多くないでしょう。
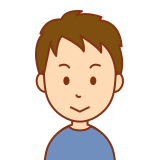
てか、ついていかなくていいです。
パワハラ?仕事を教えてくれないワケ

では、なぜ仕事を教えてくれない人は一定数いるのでしょうか。
- 会社の文化
- 新人/若手に伸びてほしくない
- 教育する側にも変化がある
それぞれについて、詳しくみていきましょう。
①会社の文化
仕事を教えてくれないのは、会社の文化が影響していることは往々にしてあります。
上司・先輩も若手時代に教えてもらえなかったとしたら、後輩に親身になって指導することはないでしょうから。
入社してみないとわからない部分ですが、教えないことが「普通」の会社は意外とあります。
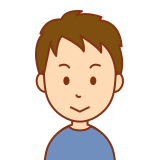
見て覚えろ、というヤツですね。
②新人 / 若手に伸びてほしくない

続いて、新人/若手に伸びてほしくないから教えないケースです。
会社員のなかには
「できる人が増えると、自分の身が危ういのでは」
と、不安な人がいます。
こういう人は、あえて新人/若手に仕事を教えず、自分が優位に立とうとします。
③教育する側にも変化がある
また、昨今では教育する側も、
「教えてもテキトーな返事されるからいいや」
「マニュアルあるし、検索すれば解決するだろうから、わざわざ教えなくていっか」
と、「教える意味がない」と判断し、細かく指導しないケースがあります。
これは過度なコミュニケーションを控える人が増えた、とも言えるでしょうか。
なので、教わる側も
「もっと教えてくれ!!!」
というオーラを出し、気前よく教えてもらうことも求められています。
【ほぼパワハラ】新人で放置された私の末路
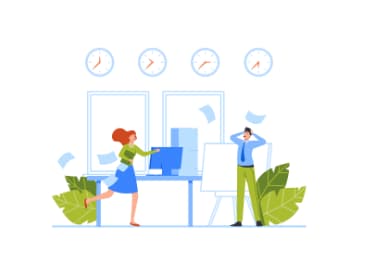
さて、少し偉そうなことを述べてきましたが、私自身も新人時代は「放置」されて苦しんでいました。
放置というか「いじめ」というか。
詳しくは「【新人で放置されて辛い】マジでしんどいなら退職はアリ?ナシ?」でお伝えしていますが、ここでも少し綴ってみます。
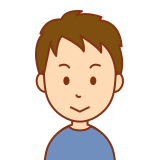
今となっては「笑い話」なので、
「ヤッバ」
「あっ、こんな人もいるんだ」
と、少し笑ってもらえれば、幸いです。
「手伝えることありますか?」 → 「ないよ」
新人の私「手伝えることありますか?」
先輩「ないよ」
私の職場では、こんなことは日常でした。
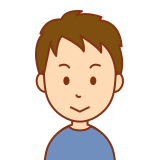
なんと寂しいコトでしょう(笑)
新人だからできることも少ないけど、なにもないんだったら、なんでここに配属なんだよって、毎日イライラしていました。
自分の存在意義を見失う

また、新人の私以外で「休日出勤」して、その対応内容のことで私抜きで会議していることもありました。
IT系の仕事だったので、トラブル発生となると、残業やら休日出勤がちょこちょこあったのですが、いつも私には連絡はなかったです。
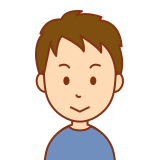
寂しいコト、この上ないですよね。
こんなことが続いたので、
「この職場に自分なんていらないじゃん」
って、自己肯定感がめちゃ下がり、しまいには入社半年くらいで、彼女にも振られました(笑)
結局、2年目で退職
結果的に2年目でやめました。
もう、メンタルはボロボロでした。
より詳しく言っておくと、「出社して打刻すること」がメイン業務で、あと8時間はヒマみたいなことも全然あったんです。
だから、
「手伝えることありますか?」
って聞くのに、
「ないよ」
で片づけられるショックさといったらもう…(笑)
【パワハラ?】仕事を教えてくれない現場での3つ解決策
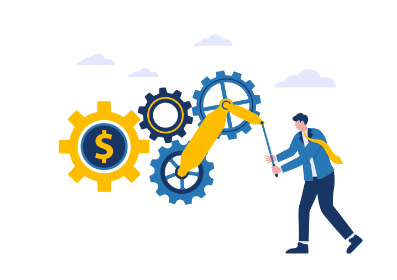
さて、本項では「仕事を教えてくれない現場での3つの解決策」をお伝えしていきます。
- 盗む
- 歴の長い人と仲良くなる
- 横展開できないスキルなら身につけない
それぞれについて、詳しくみていきましょう。
①盗む
1つが「盗む」です。
見て覚えるもそうですが、もっとセコくてもOK。
例えば、
先輩・上司の「個人フォルダ」を覗き、「マニュアル」的なのがないか調べる、的な。
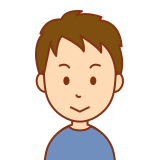
使える手は何でも使いましょう。
②歴の長い人と仲良くなる

続いて、歴の長い人と仲良くなる、です。
言い方を変えると、「ある程度何でも話せる人」をみつける、ですかね。
困ったときに、コミュニケーションをとるか/とらないかで迷ってしまう方は、頑張って「そこそこ仲良し」な人をつくりましょう。
③横展開できないスキルなら身につけない
さいごは、もはや学ばない、です。
詳しく言うと、
私の職場がそうだったのですが、ほぼ「その現場」でしか使わないスキルだと、頑張って身につけてもあまり意味がありません。
んで、そんな現場で「教えてくれない」なら、自分が無理に頑張る必要ってあるのかな、と。
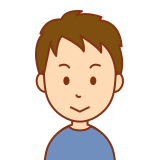
私は「ない」と判断したので、2年目でやめました。
詳しくはこちらの記事でお伝えしているので、ぜひご覧ください。
関連記事:【第二新卒は人生終了だった?】2年目でリタイアした男の末路
仕事を教えてくれないから退職するのはアリ?

では、仕事を教えてくれないことを理由に「退職」って、ホントはどうなのでしょうか。
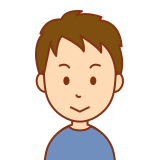
本項で詳しくお伝えします。
退職は早い可能性はある
正直、少し早い気もします。
私の職場ほど「扱いがひどい」というなら別ですが、仕事を教えてくれないという理由だけで「転職する」のは少し早いです。
というのも、別の部署はどうかわからないですし、身につくスキル・経験によっても違うからです。
(逆に身につくスキルもしょぼそうなら、早く転職した方がいいと思います。)
けど、人を大事にしない会社に未来はない

ただ、1つ言えることは「人を大事にしない会社に未来はない」ということです。
社員を大事にできない会社は、ある一定ラインで成長が止まる傾向にあります。
離職率が高く、優秀な人材が集まらくなるからです。
事実、
私の会社は、若手の離職率が高い傾向がありました。
転職活動をスタートしておくのが吉
なので結論は、退職は気が早い。
けど、転職活動は始めて、他の会社で働くという「選択肢」をもっておくことが重要
と、なります。
もちろん、転職すれば全て解決ではないですが、「いざとなれば転職できるんだ」と思えることが、あなたの心のゆとりにつながりますよ。
当サイト「若手社員のお仕事相談室」のおすすめする転職サービスは、下記にまとめてみたので、ぜひ参考にしてください。
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
 |  |  | |
| サービス名 | マイナビジョブ20’s | Re就活 | doda |
| 求人数 | 4,800件~ | 10,000件~ | 200,000件~ |
| 第二新卒 | ◎ | 〇 (20代向け) | △ (全世代対象) |
| 特徴 | ・第二新卒専用転職エージェント | ・20代の転職サイト ・無料の適職診断 | ・日本最大級の転職サイト ・キャリアアドバイザーの質が高い |
さいごに
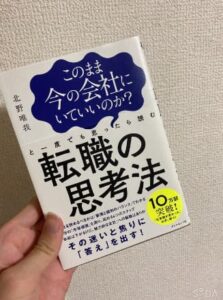
20万部以上のベストセラー『転職の思考法』に、こんな言葉があったので、紹介させてください。
今の会社では活躍できなかったとしても、違う場所で輝ける可能性がある人はたくさんいる
仕事を教えてくれないような環境では、誰しも輝こうにも輝けません。
シュートを打とうにも、味方のはずの上司というディフェンダーが立ちはだかるワケですから。
ぜひ、自分が輝ける環境を探す努力は惜しまないでくださいね!
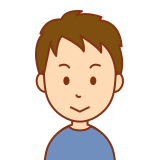
さて、今回は以上。
ご紹介した転職サービスはこちらです。
この度は、ありがとうございました。
ぜひ、当サイト「若手社員のお仕事相談室」の関連記事もご覧ください。